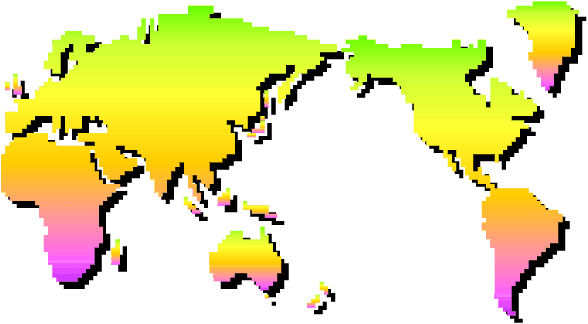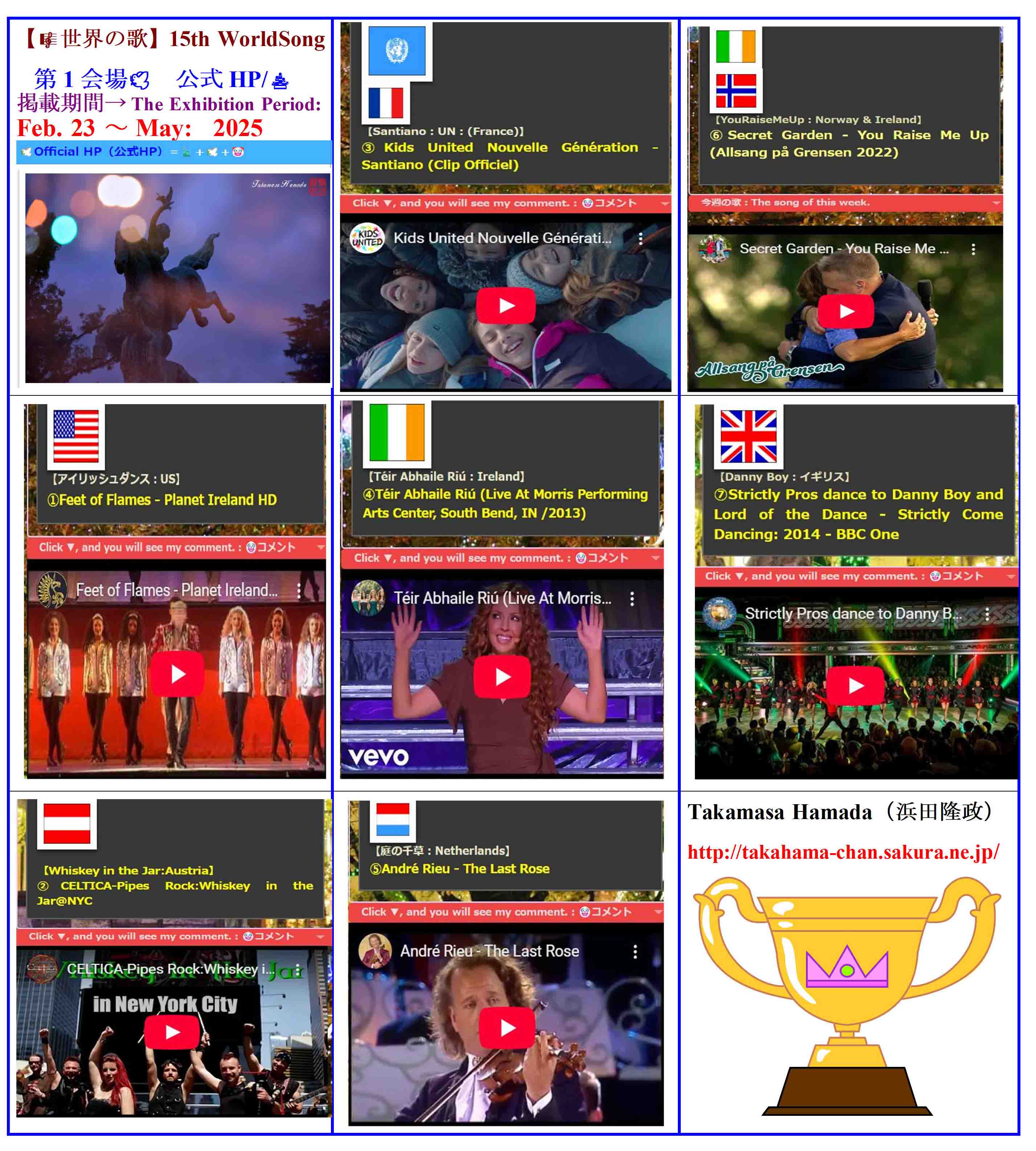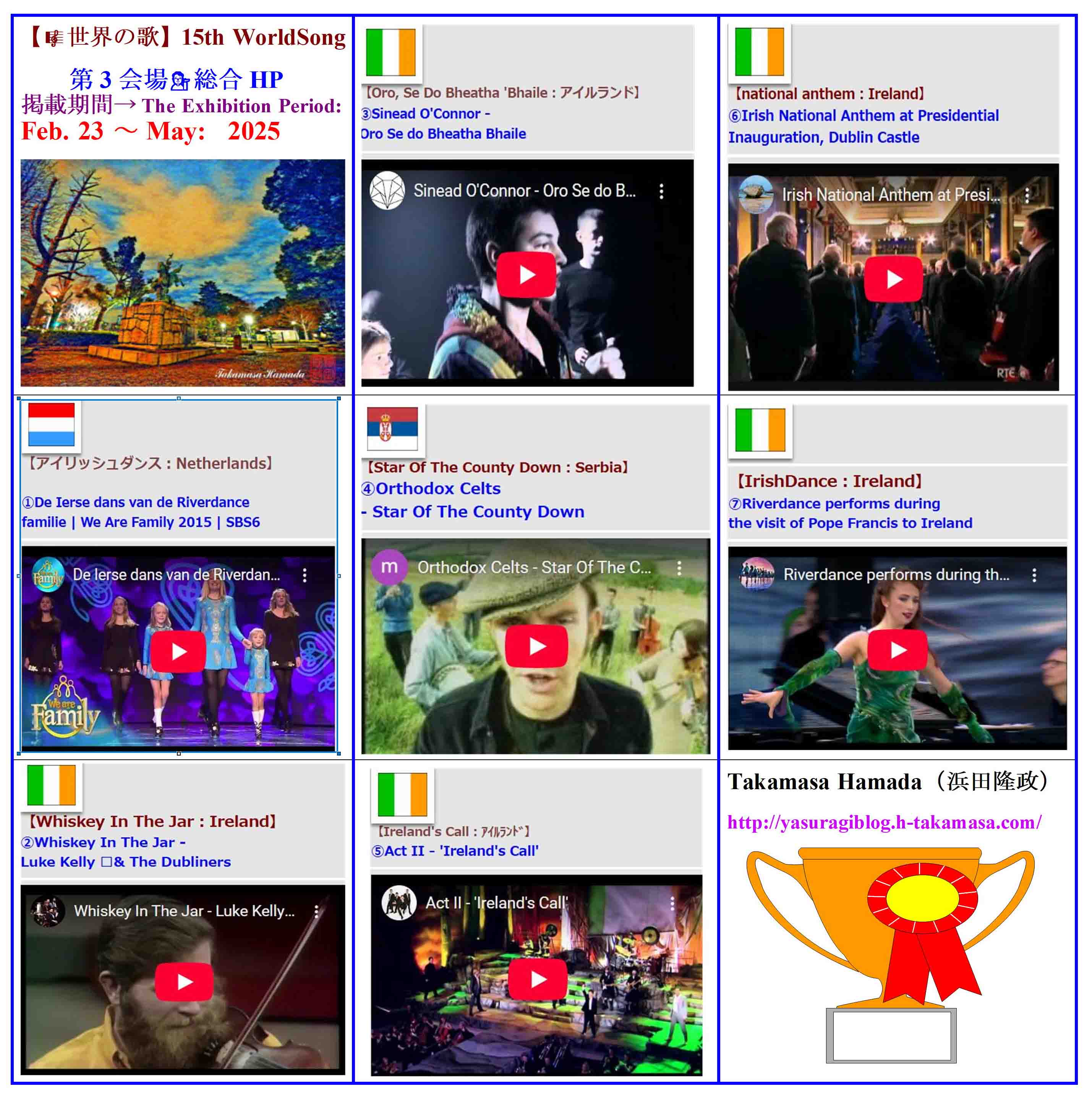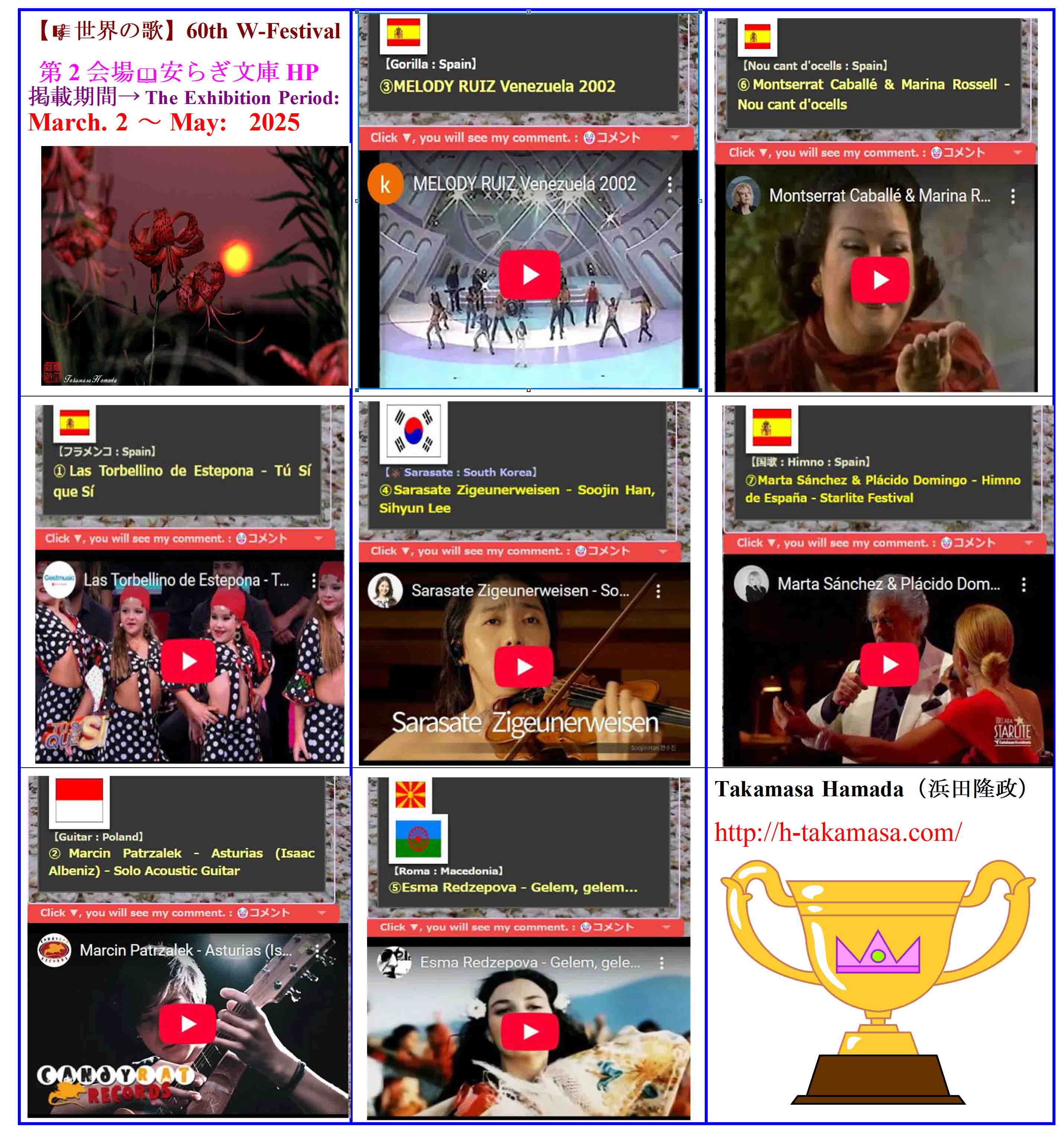公式Blog→夢か-11:光の魔術師・緑川洋一(1)写真とは何か
【緑川氏関連掲載予定内容】
夢か現実か・写真家緑川洋一(1)写真とは何か
夢か現実か・写真家緑川洋一(2)彼の遺言
夢か現実か・写真家緑川洋一(3)彼の忠告「写真は引き算」への反論
※ただし、(3)は都合で省略するかもしれません。
(A)写真家・緑川洋一氏との出会い。
緑川氏とは夢か現実かではなく、1996年7月5日(金曜日)に、緑川洋一写真美術館でお会いし、緑川氏の写真集にサインをしていただき、その写真集を購入をしている。そこで、緑川氏との出会いについては夢か現(うつつ)かとすべきではなかったかもしれない。実際に、1996年から98年にかけて、彼の美術館には五度行っているのだから。
しかし、自家用車に乗られなくなり、彼の美術館には行けなくなってしまった。すると、今度はテレビを通じて、いろいろとアドバイスをされたような感じを受けた。写真は引き算などである{(3)参照}。また、彼が死亡する直前には光る海の撮り方の具体的技法もテレビを通じて伝授された{(2)参照。}
緑川洋一氏について紹介しておく。緑川洋一(みどりかわ よういち、1915年3月4日 – 2001年11月14日)は、写真家、歯科医師である。生来の名は横山知(さとし)で、二科会写真部会員であった。彼は写真家集団「銀龍社」の関係で、米子の写真家・植田正治、東京の秋山庄太郎両氏らと親交があった。特に、植田氏とは生涯に亘(わた)り親交を厚くしていたと聞いている。その関係で土門拳などとも親交をもたれていた。
緑川氏はその作風から「色彩の魔術師」「光の魔術師」と呼ばれていた。シンガーソングライターの福山雅治氏がカメラ・写真関連で植田氏の影響を受けたように、私も緑川氏の影響を幾分うけていたときがあった。
今回の出会いでは緑川氏が亡くなられる直前に、彼の技法を公開されたので、そのときのメモを(2)で公開し、彼の技法を写真に興味のある方と共有したいと考えている。また、緑川氏が「写真は引き算」であるとよく言われたが、あるときに私にも言われた気がしたため、その件に関しての言い訳を(3)でしている。
(B)写真は哲学・1―写真技法について。
現代の科学では、写真は目で見える通りには絶対に写らない。嘘(うそ)と思えば、目の前の畑を写し、それをプリントアウトして、写した畑に持って行き、並べて比べてみるがよい。随分違っているはずである。さらに、仏像や人間を撮影する角度が一度違えば人に与える印象は随分違う。また露出を操作すれば若く見せたり、太って見せたりすることもできる。見合い写真をみて気に入り、いざ見合いすると随分顔が違うということはよくある。
勿論(もちろん)、カメラのセンサーと人間の脳では色の認識が違う。人間の目では裸電球でも、蛍光灯でも、LEDでも同様の白色に見える。しかし、カメラの側(かわ)はフィルムでも、デジタルでもホワイトバランス調整をしない限り、裸電球(タングステン)の光は黄色かオレンジに、蛍光灯は緑に、LEDは青色に写る。
要するに、現代の科学では写真は現実と同じには写らない。 そこで、プロのカメラマンたちはこの壁にぶつかったときに、思考し、いろいろと工夫をする。拙著『日本のフィクサーME』第3章第1節から一部引用する。
《引用開始》
次に『写真集・水俣』の簡単な解説をする。カメラマンの端くれでもある私から見ると、一流のカメラマンは各人がそれぞれの写真哲学を持っている。
植田正治(しようじ)氏ならば、「カメラを向ければ人は意識する。それならば逆に意識させて撮る」、あるいは、「人物をオブジェの如くにして撮る」であろうか。
緑川洋一氏ならば、「写真は見た通りには、現代の科学では絶対に写らない。ならば、より強調して表現すべきである」であろうか。
ユージンスミスの場合には、「人間の内面・本質を抉(えぐ)りとるが如く写す」である、と、私は解釈している。 作品・『写真集・水俣』の中で、彼は人間の内面を抉る如く撮影方法で水俣での人間模様を描(えが)くことにより、世界から水俣病をなくし、日本の水俣病患者を救済しようと考えた、と私は解釈している。次に、『写真集・水俣』に掲載されている人間模様を簡単に紹介する。 まず、スミスは、写真集『MINAMATA』の刊行に当たり、彼が描きとろうとしたものについて、次のように述べている。……
《引用終了》
土門拳さんが、鳥取砂丘は広いため、全部を写しきれない。そこで、彼は逆をやったことは有名である。砂丘に下駄(げた)などをおき、砂丘全部を写さずに一部だけを切り取って写し、見た人に逆に砂丘は広いことを人間の脳の中で再現しようとしたそうである。 だが、それ以上にもっと大きな写真哲学がある。私は唯物論者だが、撮影だけは観念論の世界の中にいる。
(C)写真は哲学・2―観念論について。
かつて、プラトンは、現実があり脳がそれを認識するのではなく、脳の中に潜在的なイメージがあり、それに類似したものを見て、脳の中のイメージが具現化するのである、と述べたと聞いている。
完璧な正三角形はこの世に存在しない。どの辺かが0.000001㎜などの範囲で違っているはずである。だから、先に人間の脳の中に正三角形のイメージがあり、正三角形に類似したものをみて、脳の中の正三角形のイメージが呼び起こされるという。
写真も同様だと思う。富士山と桜を見て綺麗(きれい)だから撮るのではない。先に、カメラマンの頭脳の中に桜と富士山をこういう形で入れ、空は何色で、雲はどういう形の雲がよいというイメージがある。そして、そのイメージに現実が一番近づいたときに撮影となる。
映画監督・故黒澤明氏も同様だったと思う。彼の脳の中にイメージがあり、そのイメージに現実が近づくのを相当気長に待っていたはずである。
写真というものは、先にイメージがあり、そのイメージに現実が近づくのを待つのであり、その逆ではない。勿論、そのイメージを得るためには何度も観察をしたり、どう表現し、何を主張したりするのかの検討が必要であろう。
土門拳さんが晩年車椅子生活となったが、彼は助手を使って撮影をし続けた。カメラやレンズを構えるのは助手である。ときにはシャッターを押すのも助手かもしれない。しかし、できあがった写真は、撮る前に土門拳さんの頭に写っていた写真と同一かそれに類似するものである。よって、これは土門拳氏の作品となる。
私の場合には酷(ひど)いものである。一方で、一見協力的にみえ、こう撮れば写真になるよ型で相手がお膳立てをしてくることがよくある。他方では、私がこう撮ろうと考えていた写真を妨害してくることもよくある。前者は協力で後者は妨害か。回答は両方とも妨害である。後者については言うまでもないが、前者について良い写真と考えているのは、私ではなく協力したと考えている人のイメージである。ならば自分で撮れ、といいたい。 協力というのは、私がイメージしている写真になることである。そのためには、人物ならば、私の指示通りに動いてくれなければならない。私の指示に従うときのみ協力であり、それ以外は前者・後者ともに妨害でしかない。
写真は観念論という立場をとっている以上、他人の頭にあるイメージで写真を撮ることは、他人の写真であり、私の写真ではない。
しかも、他人の頭にあるイメージはステレオタイプ化されており、作品とはならない。作品にはオリジナリティが求められる。 浜田隆政写真物語・技能の間で、「失敗写真は宝の宝庫」というテーマで特集を組む予定でいる。思いもしない形での失敗写真は、先人の編み出した技法にはない。何故(なぜ)ならば、通常の方法では起こらない形で失敗をしたのだから。そこには前人未踏のアイデアが凝縮されているときがある。その失敗写真を見て、脳が活性化して、オリジナル技法が生まれる。
恐らく、流し撮りなどの技法は失敗から生まれたと想像している。この失敗技法の一つとして、フィルム式カメラ時代に、誤って裏蓋(ぶた)をあけると、オレンジ色の色がつき、そこから面白い写真のアイデアがでたことがある。
ならば写真は絵と同一ではないか。その回答は今回できない。緑川洋一氏などは絵と写真の狭間(はざま)で葛藤(かっとう)したと思う。本来画家を目指していた植田氏も同様と思う。
次回は、光の魔術師・緑川洋一氏が死ぬ直前に、テレビを通じて、彼の技法を公開したときのメモを公開する。絞り・シャッタースピードやフィルターの使いかたに関する具体的な秘伝の公開である。この技法公開の翌年頃彼は亡くなった。その後で、このときの映像は再放送された。
追伸。
価格ドットコムなどを見ていて、やれ大三元(f2.8の明るいレンズズーム)を持つのが一番良いなどの風潮が見うけられるときがある。ところが、内容全体を読んでいくと、ルイビトン感覚なのに驚かされるときもある。大三元は重たい。本当にそうした器財を運んだことがあるのだろうか、と不思議に思うことがある。
私が1997年にフィルム式カメラ・F5を購入する際に、ある場所で出会ったカメラマンが私にアドバイスをした。「ダンベルをやっておけ」、と。
私はカメラマンではないし、写真展も開催する気もない。しかし、プレゼンテーション屋であり、物語展は開催する気はある。そのときに写真は大きな武器となる。そこで、カメラもレンズも……重要な商売上の武器である。
それらを十分活用できるようにするため、再度、腕立て分割合計500回、腹筋分割合計300回、スクワット分割合計300回、ブリッジ50回、ダンベル、エキスパンダ、何よりも柔軟体操を十分にするよう心掛けるつもりでいる。ここだけは観念論ではなく、唯物論の立場である。